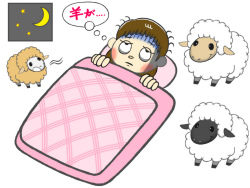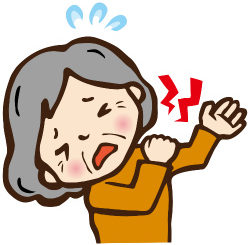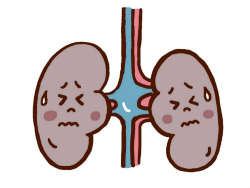RSウイルスの症状とは|おとなも感染するの・潜伏期間や治療法は?

もくじ
rsウイルスとはどんなウイルス?
RSウイルスは、1956年にアメリカの学者等によって発見され、世界で年間に3400万人の5歳未満の小児が罹患する風邪のウイルスの一種だそうです。
1歳までに75%、2歳までに95%、3歳までにほぼ100%の子供がかかると言われているそうで、9月頃から流行しピークは1~2月とされていましたが、近年では夏季から流行が始まるようになってきているそうです。
また、乳児期以降も何度も上気道感染を繰り返すそうですが、初期感染よりも軽症で鼻風邪のような症状だそうです。
しかし、小児細気管支炎の原因となる微生物の5割から8割はRSウイルスだそうで、生後3ヶ月未満の乳児や未熟児、心臓や肺に基礎疾患がある子どもなどは、重症化リスクが高いそうです。
rsウイルスの潜伏期間
潜伏期間は4日から7日間で、初期は風邪のように鼻汁や微熱などの症状が始まり、発症後3日目頃から呼吸をするときに、ヒューヒューと音がする喘鳴(ぜんめい)や持続性の咳などの症状が起こります。
最終的に約3割が細気管支炎や肺炎になるそうで、細気管支炎を起こすと喘息のようにゼイゼイと音が出るようになり、血中酸素濃度が低くなれば入院が必要になります。
おとなも感染するの
RSウイルスは子供に多いですが、ウイルス感染症なので大人にも感染するそうです。
RSウイルスは風邪のウイルスの一種なので、何度も感染しますが、おとなの場合は免疫力が強いので鼻水や軽い風邪のような症状が起きる程度だそうですよ。
なので気がつかず、赤ちゃんにうつしてしまうことがあるそうなので、十分に注意が必要です。
乳幼児がいる家庭では、外から帰ったら必ず手を洗い、せきやくしゃみは飛まつが飛ばないよう注意し、おもちゃやドアノブなどをこまめにアルコールで消毒するなど感染対策を心がけましょう。
ただし、免疫力が落ちていたり、持病がある場合などは、大人でも重症化する危険性があるそうですので、十分に注意してくだい。
rsウイルスの治療法は?
rsウイルス感染症に対する特効薬はないそうですが、細菌性の感染症と合併する可能性は低いそうで、抗菌薬も必要ないそうです。
消化のいいものを食べ、ゆっくり休み、十分に睡眠をとりましょう。
ただし、まれに急性中耳炎や肺炎、気管支炎を発症する危険性はあるそうで、リスクの高い子供には、流行開始前から流行期の間に月1回ずつの免疫グロブリン注射を予め打つことで、重症化を予防することが期待できるそうです。
子供の様子が普段と違うと感じたら早めに小児科を受診しましょう。
おとなの場合は内科や呼吸器内科を受診しましょう。
子供の活動の基本は食べる、寝る、遊ぶなので、2食続けて食事が取れなかったり、ミルクを半分以上残したり、痰が詰まってねれない、呼吸が苦しくて遊べない時などはすぐに受診しましょう。






 プロフィール
プロフィール