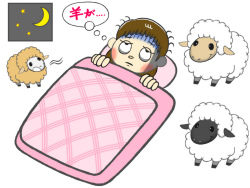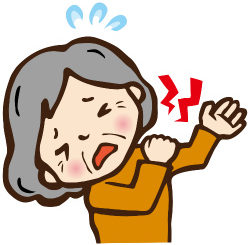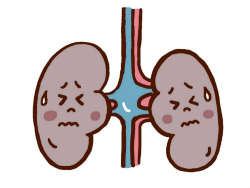へえ! 公衆電話の使い方知らないんだ

もくじ
公衆電話の使い方を知らない子供たち
携帯電話が普及して、ほとんどの人が携帯電話やスマートフォンを持っているので、最近は公衆電話を殆ど見かけませんね。
なので最近の子供達は公衆電話の使い方を知らない子が多いそうです。
それどころか公衆電話を知らないという子もいるそうで、あわせて84.3%もいるそうですよ。
でも災害時などの緊急時には公衆電話が活躍します。
災害時優先電話
災害などの緊急時には電話が混み合い通信規制が行われることがありますが、公衆電話は災害時の緊急時でも通信規制されず優先的に取り扱われるので、災害時等の有効な通信手段です。
通信ビルからの給電
公衆電話はNTTの通信ビルから電話回線を使って電力の」供給を受けているので、停電時でも電話をかけられます。
公衆電話の特徴
携帯電話などが普及して急速に減少した公衆電話ですが、東日本大震災をきっかけに災害発生時に無料で使用できる「災害時用公衆電話」(特設公衆電話)の設置が進められています。
いざという時のために公衆電話の使い方を、子供たちや使い方がわからない人に教えましょう。
公衆電話の使い方
公衆電話には、アナログ公衆電話とデジタル公衆電話の2種類あります。
通常時の使い方に違いはないですが、停電のときや無料化(災害発生時)されたときの使い方が違います。
通常時の使い方
① 受話器を手にとる
② 10円か100円玉またはテレホンカードを入れる
・100円玉は10円玉より長く話せるけど、おつりは出ません。
③ 電話番号を押す
・「ツー」という発信音が聞こえてから電話番号を押しましょう
④ 受話器を置く
緊急時の使い方【110(警察)、118(海上保安)、119(消防、救急)】
◎デジタル公衆電話
基本的に通常時の使い方と同じですが、10円玉や100円玉、テレホンカードは不要です。
受話器を上げて、そのまま110番等を押してください。
◎アナログ公衆電話
基本的に通常時の使い方と同じですが、10円玉や100円玉、テレホンカードは不要です。
受話器を上げて、緊急通報ボタンを押した後に110番等を押してください。
停電時の使い方
液晶ディスプレイや赤いランプが消えています。
◎デジタル公衆電話
液晶ディスプレイが消えています。
基本的に通常時の使い方と同じですが、テレホンカードは使えません。
◎アナログ公衆電話
赤いランプが消えています。
基本的に通常時の使い方と同じですが、テレホンカードは使えません。
無料化措置時の使い方(災害発生時等)
◎デジタル公衆電話
基本的に通常時の使い方と同じですが、10円玉や100円玉、テレホンカードは不要です。
受話器を上げて、そのまま電話番号を押してください。
◎アナログ公衆電話
基本的に通常時の使い方と同じですが、10円玉や100円玉、テレホンカードをいったん投入します。
受話器を上げて電話番号を押し、会話終了後に10円玉や100円玉、テレホンカードがそのまま返却されます。
公衆電話の設置場所の確認
公衆電話の設置場所は、NTTのホームページから全国の公衆電話の設置場所を調べることができます。
自宅の近くや通勤通学路など設置場所を確認しておきましょう。
◆東日本エリアの公衆電話設置場所情報
◆西日本エリアの公衆電話設置場所情報

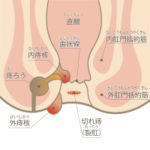




 プロフィール
プロフィール